知り合ってからチナはかれこれ15年、サコはかれこれ8年。
芸もひとも、とにかく面白い。
年の暮れに1時間ほど話を聴く機会があったので、それをまとめて、当コラム愛読者のみなさまにお送りすることにしました。
サコチナプレゼンツ! オオタスセリ、こんなおんなです!

ひとりコントやギター弾き語りのコミックソングで、観客を笑い転げさせる芸人。
今日では、テレビに出たいから芸人になる者と、芸が好きだから芸人になる者とがある。スセリちゃんは確実に後者。
三年前、芸能プロダクションを離れ、完全フリーになった。マネジャー、付き人、なにもかも自分でしている。
かつて、お笑いコンビ〔コントペコちゃん〕でデビューしたころは、テレビにも出ていたが、今はほとんどぜんぜんまったく出ない。拒否しているわけではない。出る努力をまるでしない結果だ。もちろん、芸の研鑽努力は激しくしている。
もっぱらライブ活動。オッカケもいる彼女の芸を、ちょっとだけ見たい向きには、YouTubeを当たるようオススメするしかない。ヒット作(歌)『ストーカーと呼ばないで』は、CD(ビクターエンタテイメント)で聴くことができる。

学生時代のアダ名が「歩く銀の鈴」。東京駅の待ち合わせポイントになるくらい、群衆から頭ひとつど~んと突き出る見事な体格で、「結婚しない女」のさまざまな場面を自作自演する。マケイヌのようだが負けていない、その微妙な真実の展開がうまい。毒の香りもほどよい。
1960年東京生まれ。鎌倉に母ほか家族と住む。本名は同音を漢字で太田寸世里。記紀(古事記・日本書紀)に登場するスセリヒメにちなんで、父親がつけた。なんと、古代史で結ばれたサコチナには、出会うべくして出会った観があるではないか。
「記紀の漢字(須勢理、須世理)は女の子らしくないというので、これに変えたそうですけどね。子どものころ聞いた由来は、やさしくて、かしこくて、勇気のあるお姫様だからって。美しい、が入ってない(笑)。でも、大きくなってから聞いたんですけど、別の意味もあったんです。スセリヒメはオオクニヌシノミコトと駆け落ちするじゃないですか。父と母は駆け落ち結婚だったんですって。それにちなんだんですね」
大学でオチケン(落語研究会)に入った。特に落語の素養があったわけではない。中学高校では「運動と勉強しかしてこなかった」ので、大学では「マジメなばかりではつまらない、カレッジライフを楽しもう」と考えていたところ、オチケンの入部勧誘が『笑点』みたいで面白かったからだ。
その先輩に新宿の末広亭へ連れていかれた。初めての寄席だった。
「あそこで本物の落語を見ちゃったら、もう、面白くて。で、お金がないですよね、学生だから。もう一度行きたいけど、どうしようかなあ、と言ってたら、先輩が、バイト募集してるって。あ、働けば毎日見られると」
「アマチュアのを見ても仕方ない」とオチケンは辞めて、末広亭で働いた。
「落語やりたいな、と思ったんですけど、そのころ、まだいなかったんですよ、女性が。関西にはひとりいましたけどね、露の五郎兵衛さんのところにひとり」
女性落語家第一号と言われる「露の都」だ。1974年に弟子入りして、現在も活躍中。上方落語女性部部長(上方笑女隊隊長)。東京では、81年に現在の「三遊亭歌る多(真打)」が圓歌に弟子入りするまで、女性落語家はいなかったらしい。84年には「古今亭菊千代(真打)」が圓菊に入門。徐々に増えて、今では4人の真打を含む20人ほどの女性が、落語家の道を歩んでいる。むろん、落語史始まって以来の最多だ。
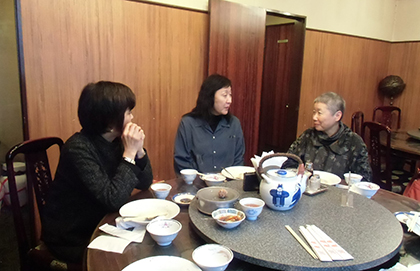
なるほど、スセリちゃんは、昨今、増加している落語オタク女子のひとりだったのか。彼女の演技には、時々、落語に似たものがある、と見てはいたのだが。
「あ、もう台本の基本も、流れも、時間帯って言うんですか、マエフリがあってこういって、というのも、似てると思います。好きで毎日聞いてましたから、意識していなくても、こうすると気分がいいっていう、落語の流れというのが体にできているので」
女性のいない落語は諦めて、一転、岸田今日子の劇団「円」に入った。
「紀伊国屋ホールで文学座の『ほととぎす』とかいうのをひとつと、今日子さんが出ていた円の、別役実さんの『雰囲気のある死体』とふたつ観て、ああもう、こっちのほうがぜったい面白いと思って、それで円を受けたら受かったので、大学辞めて、入ったんです。なまじなことやってたら多分ダメだと思って。そのころ、まだ父が生きてたので、2年で大学辞めたいんですけど、と話したら…ふふふ、大学行くとき、父親は短大いけって言ったんですけど、私が4年制いくって言って、いったんですよ。それで父親がね、スセリちゃん、やっぱり短大にしときゃよかったなって(笑)はあい、すみませんでしたあって」
舞台デビューはかのシェイクスピア『夏の夜の夢』。
「…の“職人”(笑)。女の子たちみんなきれいなかっこしてるのに、私だけ、えっほえっほえっほ、劇の稽古をしようぜ、とか言って。女では私だけ口紅もつけずにドーランだけ、私だけ男の役だから。見越しの松とか言って壁やったんですよ、壁を(笑)。もう、がっかりでしたけどね」
2年がんばったが芽が出なかった。
「それだと食べていけないので、悔しいなあと。チケットを頭下げて売らなければならないのが悔しくて。この資本主義の世の中に、価値が無いから、頭下げないと売れないんだなと、ちょっと子どもながらに思ってて」
そんな時、テレビの演芸番組を手伝っていたオチケンの先輩から、「今度、シロウトの参加番組、勝ち抜き戦をやるんだけど、出ないか」と話があった。先輩の呼び出しに応じていくと、漫談で出ようとしている「ちっちゃな女の子」を紹介され、大と小とで〔ペコちゃん〕なるコンビを組むことになった。それで出演したところ、
「ビギナーズラックで、プロのひとに勝って、優勝しちゃって、それで事務所に入って、お笑いをやることになったんです。4、5年なんですけどね、ふたりでやってたのは。ゆかりちゃん(相方)、子どもができたもんですから。どうする?ったら、産むっていうから、じゃ…じゃあ…休憩?って感じになって。で、そうしたら次、二人目ができたっていうから…あ、そう…ってんで。困ったな…私も結婚するのかな、と思ったが、することもなく(笑)。そいで40になるときに、もう、辞めるか、なにかやるかだな、やっぱやってみよう、と思ってひとりコントを始めて。ちょうどジアンジアンが終わるとこだったんですよね」
小劇場文化を支えた渋谷ジアンジアンは、1996年7月に開場し、2000年4月に閉じた。その最後に、初のひとりコントで「出してもらった」。しかし、
「ウケなくて。もうびっくりするぐらい。誰もわかんなくて、私がやってること。私はおもしろいんですけど。びっくりするぐらいウケなくて。へええ、と思って。そっから、やってみようと思いました。悔しいんで、このままじゃ」
どうやら「悔しい」が原動力。年に何回か、下北沢の小劇場を借りて公演するようになった。続けるうちに、だんだんウケるようになり、仕事もくるようになった。

「ところが衣装が大変なんですよ。7作7役やると7つ、それに当時は靴も同じじゃいけないと思ってたので、靴も7足、地方公演なんかだと、これ持ち運ぶのが大変で」
そんな時、放送作家でラジオパーソナリティ、落語や歌も演る「奥山侊伸先生」(チナには昔なじみのオクちゃん)のステージを観た。落語とコミックソングを交互にやる構成だった。「これなら同じ衣装でいくつも演れる」とひらめき、ギターの練習と曲作りを始めた。それで最初に作ったのが『負け犬の歌』、次が『ストーカーと呼ばないで』。
そのころ、永六輔、矢崎泰久、小室等、中山千夏がやっていた講座「学校ごっこ」に、永さんの引きで出演が決まっていた。そこで、初演しようと思って、
「永さんに、歌を聞いてください、と言ったんですよ、楽屋で。そうしたら、「聞きません」(笑)。なんかあって機嫌が悪かったんですね。どうしようか、と思ったんですが、コントでは認めてもらってたので、一応ギターを用意して、壇上に上がってコントをやって。それから、客席の永さんに、ギターがあるんですけど、歌っていいですか、と聞いたら「お客に聞いてみれば」と言われたんですね。そこで、歌っていいですか、と尋ねたら、あそこのひとたち優しいから拍手してくれて」
曲はウケた。終演後に永さんも、「おもしろかった、明日、ラジオにきなさい」と言い、永さんが司会する長寿番組、TBS「土曜ワイド」で披露した。これがブレイクのきっかけだった。
「終わったら、視聴者から電話がいっぱいきて、今のはなんだ、心に残らないで耳に残る歌だ(笑)。どんなヤツが歌っててCDはどこから出てるんだ、と」
ラジオの力、恐るべし、前座で出ていたステージを、前座だけ見に来るリスナーまで現れた。
反響に意を強くしたスセリちゃんは、1万円を出資して、自ら曲をレコーディングした。あとは毎日、うちでCDに焼き、自分で描いたイラストでカバーを作り、公演の時に手売りした。即日で100枚売れた。通算、1000枚近くがあっという間に売れた。
「最初からそうとわかっていたら、頼んで作ってもらいましたよ。でも、100枚作って売れるかな、どうかな、と始めたもので。70枚売れれば録音代とCD代とペイできる計算だったんです。それがすぐ売れちゃって。で次のステージのお客さんの予定数、作っていくとまた全部、売れる。その繰り返しで、毎日毎日、たいへんでしたよ。980枚くらいまでいった時に、ビクターから話があって、出すことになって、そうしたらもう自分で作って売っちゃいけないんですね、今後はやめてください、と言われてやめましたが」
そんなこんなで今日にいたる、とスセリちゃんは駆け足の来し方を締めくくった。

ところで、チナの私見では、女性コメディアンには、人気獲得を阻む大きな問題がある。
しとやかに美しく控えめに、といういわゆるジェンダーが、お笑い芸の幅を限ってしまうからだ。その次第は、お気に入りの男性お笑い芸人を思い浮かべて、もしあれが女だったら、と想像してみるとわかる。はしたないとかよくやるよとか態度デカすぎとかいう感想が少しでも浮かんだら、それがジェンダーの働きだ。
男ならただ笑ってしまう言動が、女だと多少とも批判のタネになる。
ちなみに、漫才に女性が多いのは、基本的に芸人同士の対話、対決であるという粉飾が、攻撃性の客への直撃を緩和するからだろう。客は、対話、対決の傍観者という安全地帯にいられる。傍観するだけなら、女性の攻撃性にも寛大になれるという寸法だ。
「女性同士の漫才でも、話はヨメにいくとかいかないとか、そういうことなんですね。自分たちがやってたコントとかは、やっぱり、最初、言われましたね。女のひとがドタバタするのはイヤだなあ、と。女のひとが騒いだり、罵り合ったりするのは、笑えない、と、それは、ものすごく言われました。それと、注文で、結婚をネタにしてください、みたいなのが多かったですね。お姉さんが結婚できなくて、妹ができるみたいな、そういう話にしてください、とか。それで、そういうネタが増えるということもありますね」
女性の人気お笑い芸人が昨今、激増したのは、世界的な女権運動の流れとともに、このジェンダーが薄れたからに違いない、とチナは考える。ひとを笑わせるという、かなり攻撃的な行動を女がすることに、世の中が慣れてきたのだ。
「今はもうだいぶ変わりましたが、私が就職するころは、女性は4年制はダメ、短大で、うちから通えないとダメ、というのがまだうっすら残っていた、そういう時でしたからね。うちはそういうことヤカマシクないうちだったし、言いたいこと言ってたからアレなんですけど…でも、やっぱり、仕事を本気でするなら男に生まれたかったな、と言ってましたね。女だと、いつやめるんだ、みたいになっちゃうし。24で芽が出なかったらやめろ、と父にもはっきり言われてましたから。24でデビューできたから辞めずにすみましたが。ま、辞めたら辞めたでまた別の人生があったんでしょうけど。でも、そういうメヤスがあったのが、ちょっとイヤだったですね。ネタにはしましたよ。クリスマスケーキと同じで、24まで。25は半額。26になると売れ残り、30、31、年越して1日になるともう腐ってる(笑)。女の仕事は腰掛けとか、女はお嫁さん要員とか、ネタにはよくしてました。腰掛けたまま20年たっちゃってさあ、根が生えちゃってさあ、とか(笑)。今は気軽に言ってます。でも、その時は、ちょっと悔しかったので、ネタにしたみたいなとこありましたね」
寄席でもお笑い界でも、いまだに男女の人口比に圧倒的な差がある。そんな土壌の上に、だれもが気づかないほど慣習化した大小のセクシャルハラスメントが生きている。
「新人のころ、3組で、男性2組と女性1組だと、必ず間に入れられるのがイヤだったんです、私は。男のチーム2組といっしょに呼ばれると、(出演の)並びが、男、女、男なんですよ、必ず。私たちは、はっきり言って、最後に出た男より、面白いと思ってたので、実力で言えば私たちが最後なのに、必ず真ん中。女は間に挟んどこう、女性を間に挟んだほうが並びがいいから、と、そういう種類の考え方ってありますね。実力だとこっちが上なのに、どうして最後じゃないのかと、ずいぶん言いましたよ。ナマイキだと言われましたけど。悔しかったですね。今だったらもうぜんぜん、ハイどうぞ、ですけど(笑)そのころは、ふざけんな、実力で決めろ、と悔しかったですね」
悔しさを原動力にン十年。おんなスセリは今日もゆく!
(オオタスセリさんの快いご協力に感謝します)